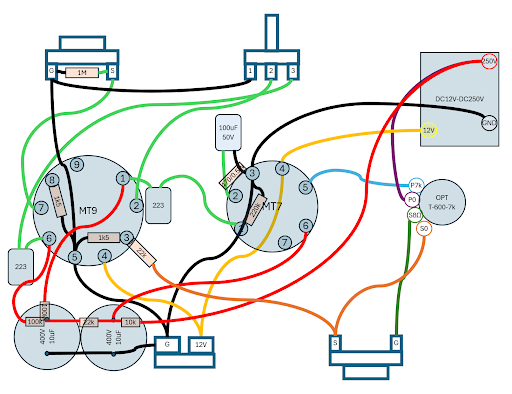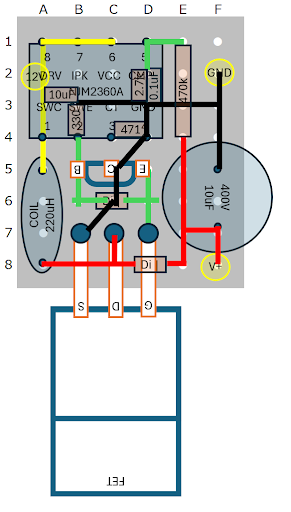Champ 5F1もどきがうまくいったので、次は5C1を作ってみる。
というのも、Mini 5F1はMT9→MT7という並びがちょっとアンバランスに見える。
また、今まで5F1しか作ったことがないので、プリが5極管のときの音も聞いてみたい。
■真空管の選定
本家は、プリ6SJ7→パワー6V6GTという構成。5極管+5極管。
プリに使えそうなMT管を調べてみると、6AU6ファミリがちょうどよさそう。
パワー管は12AQ5を使いまわしたいので、プリ12AU6→パワー12AQ5の組み合わせに決定。
■回路図、実態配線図
回路図はhttps://www.google.com/search?q=5C1+schematicで探してください。
よくあるシングルアンプだが、初段はグリッドリークバイアスによって部品点数を削減しているのが面白い。
プレートがそのまま接地され、第1グリッドにはグリッドリーク抵抗5MΩをつけて、コンデンサを挟んで入力を受けている。
このカップリングコンデンサを除くと、初段のバイアスが崩れるので要注意。
常備部品に1Mを超える抵抗がなかったので、急遽aitendoで部品を追加した。
■実物
で、できたのがこれ。
前作と違い、パワー管を少し左にオフセットさせている。
5F1で感覚をつかんだので、相当早く作れるようになった。
1番時間がかかったのは、プリ管に採用した12AU6のオークションでの到着待ち。
はらわたはこんな感じ。
だんだん感性がマヒしてきて、まだまだスペースがあるように感じてしまう。
今回は、3Dプリンタの活用範囲をさらに広げた。
FET固定だけでなく、コンデンサの固定台も作成。
OPトランスのネジと共締めできるようにしている。
アンプが小さすぎてエフェクターがバカでかいように見えてしまう。
ボリュームを絞ったときのコントロールのしやすさはこちらのほうが明らかに上。やはり12AX7の2段はゲインが有り余っているのでは?