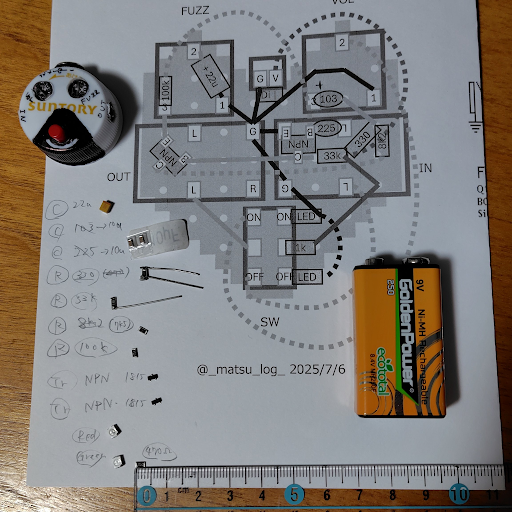■ウィーンブリッジ発振回路
1.6MHzの正弦波を簡単な部品で作りたい。
OpAmpを使う方式として、ウィーンブリッジというものがあるらしい。
https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/1552/
意味合いとしては、G=3の非反転増幅回路にバンドパスフィルタをつけたもの、と言えるらしい。
このバンドパスフィルタは、R1=R2, C1=C2のとき、f=1/(2πR1C1)となる。
逆算すると、1kΩと100pの組み合わせにすればよい。
単電源での実装はこちらがわかりやすい。
https://araisun.com/wien-bridge-oscillator.html
上記を参考に、回路をシンプル化しつつ、OpAmpの余った分をバッファアンプとした。
こちらを、実際に回路を組んで試してみる。
 51kΩ+104,G=3 31Hz
51kΩ+104,G=3 31Hz
 1kΩ+104,G=3 1.59kHz
1kΩ+104,G=3 1.59kHz 51kΩ+102,G=3 理論値31.2kHz
51kΩ+102,G=3 理論値31.2kHz
 1kΩ+102,G=3 理論値1.6MHz
1kΩ+102,G=3 理論値1.6MHz
 1kΩ+102,G=6 理論値1.6MHz
1kΩ+102,G=6 理論値1.6MHz- 4558DD
- TL072P
- TA75558P
- LF353N
- JRC2737D
- MCP6022
 1MΩ+102,G=3 1.45kHz
1MΩ+102,G=3 1.45kHz 51kΩ+102,G=3 27.9kHz
51kΩ+102,G=3 27.9kHz以下、https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.htmlのコード。
$ 1 0.000005 0.41233529972698213 50 5 43 5e-11
r -96 272 -96 224 0 10000
c 224 224 160 224 4 0.000001 -10 -10 0
a 80 224 160 224 8 15 -15 1000000 0 0 100000
a 224 208 304 208 8 15 -15 1000000 0 0 100000
r -96 192 -96 144 0 10000
w -96 192 -96 208 0
w -96 208 0 208 0
w -96 208 -96 224 0
w 224 192 224 144 0
w 224 144 304 144 0
w 304 144 304 208 0
w 304 208 336 208 0
r 80 208 32 208 0 10000
g -96 272 -96 288 0 0
R -96 144 -96 112 0 0 40 9 0 0 0.5
r 128 144 80 144 0 22000
w 80 208 80 144 0
w 128 144 160 144 0
w 160 144 160 224 0
r 160 272 160 224 0 1000
c 144 304 112 304 4 1e-10 -10 -10 0
c 0 288 0 240 4 1e-10 -10 -10 0
w 160 272 160 304 0
w 160 304 144 304 0
w 112 304 80 304 0
w 80 304 80 240 0
w 80 304 0 304 0
r -48 288 -48 240 0 1000
w 0 288 0 304 0
w 0 304 -48 304 0
w -48 304 -48 288 0
w -48 240 0 240 0
w 0 240 0 208 0
w 0 208 32 208 0
O 336 208 368 208 0 0
o 34 1 0 4098 20 0.1 0 1
38 1 F1 0 0.000001 0.000101 -1 Capacitance
38 0 F1 0 1 101 -1 Resistance